はじめに
家族が亡くなった後に直面するのが、銀行口座の処理です。
「どのタイミングで止まるのか?」「お金はどう引き出せるのか?」といった疑問は多くの方に共通します。この記事では、
- 銀行が口座を凍結する流れ
- 相続人が行う手続きの概要
- 注意点と備え
を整理して解説します。
1.【銀行】口座はいつ・どうやって凍結される?
死亡が知られると凍結される
市区町村へ死亡届を提出しても、それだけでは銀行には通知されません。
銀行が死亡を知るのは、多くの場合、遺族や関係者からの連絡を受けたときです。この時点で口座は凍結され、入出金は一切できなくなります。
凍結されるとどうなるか
- ATM・ネットバンキングが利用不可になる
- 公共料金・サブスクの引き落としが停止
- 年金や給与の入金も不可
料金の未納や支払い遅延につながることもあるため、凍結後は関係先への速やかな通知と対応が必要です。
2.【相続人】凍結された口座の解除方法
凍結解除には、相続手続きが必要
銀行は「誰に払えばよいか」を判断できないため、法定相続人による正式な手続きが求められます。
手続きの流れ(概要)
以下は一般的な流れです:
- 相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、法定相続人を明らかにします。 - 遺産分割協議
相続人が複数いる場合、どの資産を誰が相続するか話し合い、協議書にまとめます。全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。 - 銀行への手続き申請
各銀行に「相続手続依頼書」など所定の用紙と必要書類を提出します。
提出書類の例
銀行により異なりますが、次のような書類が一般的です。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍・印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 相続依頼書(銀行所定の書式)
- 通帳・キャッシュカード
- 本人確認書類
銀行により手続き完了まで1〜2週間程度かかる場合があります。事前に必要書類を確認し、準備を進めましょう。
3.【補足】仮払い制度について
相続手続きが完了する前でも、葬儀費用など緊急性の高い支出に備え、2020年の民法改正で「仮払い制度」が導入されました。
主な内容
- 1金融機関あたり「150万円 × 法定相続分」まで
- 相続人の単独申請で引き出し可能
- 葬儀代・病院代・公共料金等に充当可
ただし、金融機関の対応有無や条件に違いがあるため、事前の確認が重要です。
4. よくある注意点と備え
他人の口座を無断で動かすのは違法
たとえ家族であっても、相続人全員の同意なく勝手に引き出す行為は、法的トラブルの原因になります。
特に、亡くなる直前や直後の引き出しは「不当利得」や「使い込み」と見なされることがあります。
複数口座の存在に注意
- 同一銀行でも支店が異なると手続きは別扱い
- ネット銀行や証券口座、外貨預金なども含めて確認が必要
生前の備えが手続きを円滑にする
- 銀行名・支店名・口座種別をエンディングノートに記載
- 最低限、家族と情報共有をしておく
- パスワード等の管理には十分注意
まとめ
銀行口座は、死亡によって自動的に凍結されるわけではありません。家族や関係者が知らせて初めて凍結され、その後の対応は相続人が担います。
凍結解除には戸籍収集や協議書の作成など、一定の準備と手続きが必要です。
生前にできる情報整理と家族との共有が、相続時の混乱や負担を軽減します。

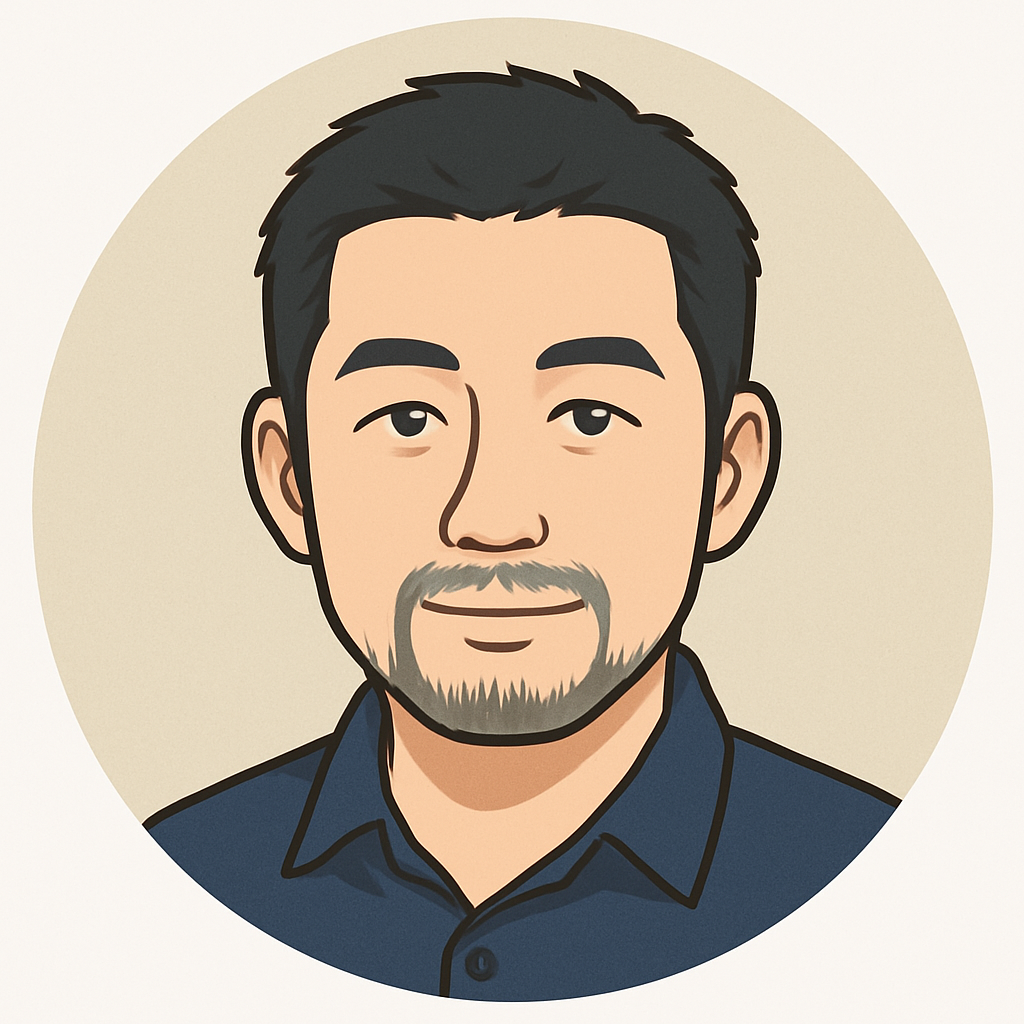

コメント