目次
はじめに
家族が亡くなった後にSNSアカウントがそのまま残っていると、なりすましや情報漏えいといったリスクが生じることがあります。
近年では「デジタル遺産」としての取り扱いも注目されており、放置せずに適切な手続きを行うことが大切です。
この記事では、主要SNSごとの対応方法と、あらかじめ備えておくべきポイントを整理しています。
なお、SNS各社の仕様や申請方法は変更される可能性があるため、最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
SNSアカウントは放置するとどうなる?
多くのSNSでは、アカウントが自動で削除される仕組みにはなっていません。
申請を行わない限り、長期間そのまま残り続ける場合があります。
放置によるリスク:
- アカウント乗っ取り・なりすまし
- 故人の名義を使った詐欺行為
- 遺族への心理的な負担
- 個人情報の流出
サービス別|SNSアカウントの対応方法
Facebook・Instagram(Meta社)
- 追悼アカウントへの切り替え:投稿や写真は残したまま、メモリアル用アカウントに。
- アカウント削除申請:親族等が死亡証明書を添えて申請することで削除可能。
※Facebookでは「追悼アカウント管理者」の事前設定が可能です。
Googleアカウント(Gmail・YouTube等)
- アカウント無効化管理ツールを事前設定することで、指定した人に通知・共有が可能。
- 死後は家族が所定の手続きを踏んで、削除や情報開示を申請できます。
X(旧Twitter)
- 遺族が申請すればアカウント削除が可能。
- 死亡証明書や申請者の身元確認書類が必要。
手続き時に気をつけたいポイント
● 必要書類を事前に確認
死亡証明書・戸籍抄本・申請者の本人確認書類など、複数の書類が求められるケースがあります。
● 処理に時間がかかることも
申請から削除までに数週間かかる場合もあります。対応は早めに行うのが安心です。
事前にできる備え
1. アカウントの一覧を残しておく
エンディングノートや紙のメモなどに、利用中のSNSやオンラインサービスの一覧を書き留めておくと、家族の対応がスムーズになります。
2. 各SNSの「事前設定機能」を活用
- Facebook:追悼アカウント管理者の指定
- Google:アカウント無効化管理ツールの利用
3. 不要なアカウントの整理
使っていないSNSやサービスは生前のうちに退会・整理しておくと、万一の際の対応が少なくなります。
まとめ
- SNSアカウントは自動で削除されるわけではなく、家族による手続きが必要です。
- 各サービスで申請方法や必要書類が異なるため、事前の確認と備えが重要です。
- 利用中のSNS一覧を記録しておく、各社の事前設定機能を活用するなど、できることから対策しておきましょう。
注意:SNSの仕様は変更される場合があります
本記事は2025年7月時点の情報を元に作成しています。
SNSごとのアカウント管理ポリシーや申請手順は、予告なく変更されることがあります。
対応前には、必ず各サービスの【公式ヘルプページ】を参照してください。

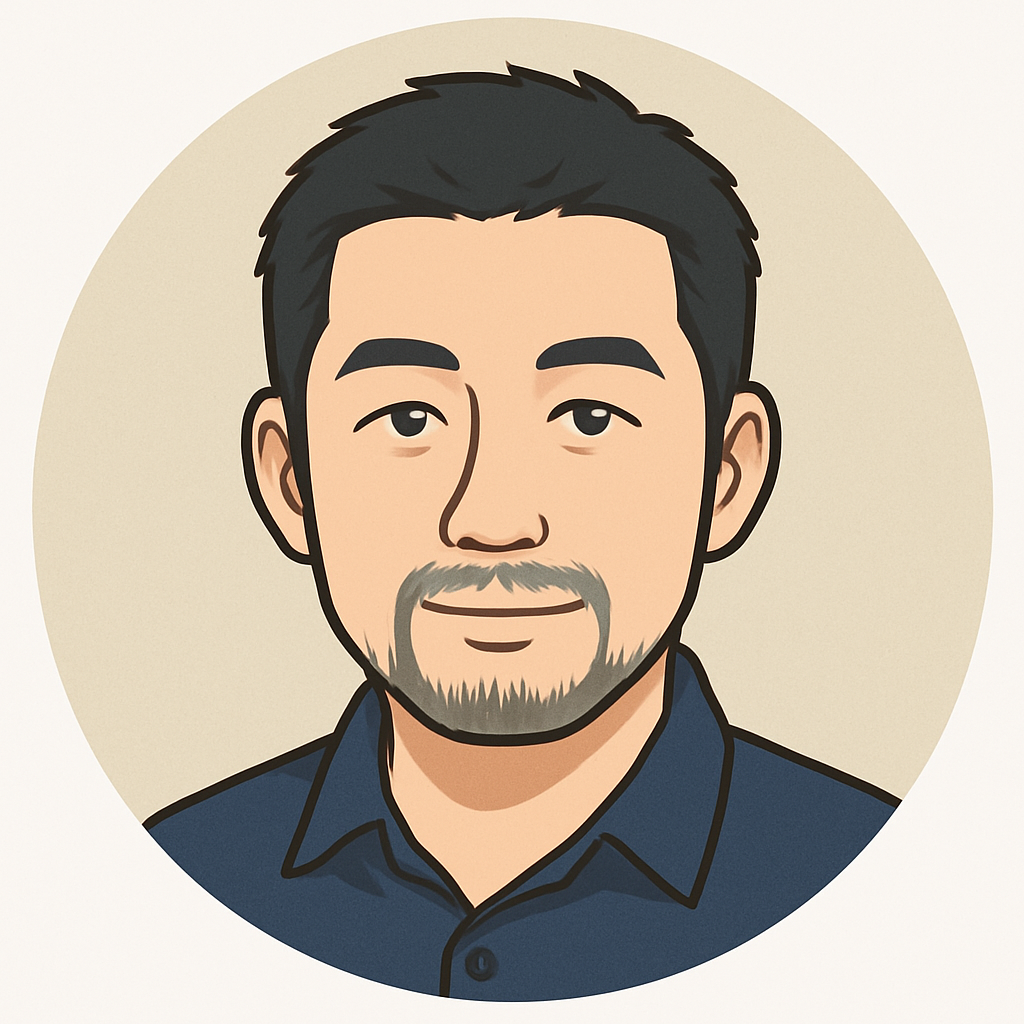
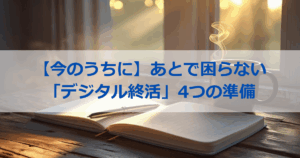
コメント