はじめに
家族が亡くなった後、自宅に届き続ける郵便物に戸惑う方は少なくありません。
故人宛の書類を放置しておくと、未払い請求や情報漏えいなどのトラブルの原因になることもあります。
この記事では、死亡後の郵便物対応について基本的な考え方と注意点をまとめました。
落ち着いて対処するための参考になれば幸いです。
郵便物はそのまま届き続ける
故人の名義で契約・登録されていたサービスからの郵送物は、自動的に止まることはありません。
何も手続きしなければ、数ヶ月〜数年にわたって届き続けるケースもあります。
届く可能性のある主なもの:
- クレジットカードの利用明細・更新カード
- 保険会社からの通知やお知らせ
- 銀行や証券会社の取引報告書
- 公共料金やサブスクの請求書
- 税金(住民税、固定資産税など)の通知
- 通販サイトやポイントサービスからのDMなど
故人に関する手続きが完了したと思っていても、意外なところから届くことがあるため、一通一通の確認が欠かせません。
郵便物の転送はできるのか?
日本郵便では、転送届は「本人」または「同居の家族」に限り有効とされています。
死亡した本人の名義での転送申請はできず、制度上の対応には制限があります。
たとえば以下のようなケースでは転送ができません:
- 故人の単身世帯だった実家 → 親族宅への転送
対応の選択肢
- 定期的に現地のポストを確認する
- 近隣の親族や知人に協力を依頼する
- 届いた郵便物をもとに、各差出人へ個別に送付停止や住所変更の手続きを行う
転送制度が使えない以上、一件ずつ地道に対応していくのが確実な方法です。
郵便物への対応で注意したいポイント
1. 中身は必ず確認する
見た目が広告やDMに見えても、請求書や重要書類が含まれている場合があります。
開封して内容を確認し、重要なものから順に対応していきましょう。
2. 個人情報をそのまま捨てない
宛名や契約番号などが記載された書類をそのまま捨てると、情報漏えいのリスクがあります。
廃棄する際はシュレッダーや溶解処理を利用するなど、個人情報保護に十分配慮しましょう。
3. 差出人に送付停止を依頼する
ダイレクトメールや通知などは、差出人に「故人の死亡」を伝えることで送付停止が可能な場合が多くあります。
少し手間はかかりますが、一度対応しておくことで今後の負担を軽減できます。
4. 防犯の観点にも注意を
ポストに郵便物が溜まり続けると、「この家は長く不在だ」と周囲に気づかれることがあります。
とくに空き家になった実家などは、空き巣や勧誘などの対象になるリスクも。
家族間で回収を分担する、信頼できる近隣者に協力を依頼するなど、郵便物を放置しない体制を整えることが大切です。
まとめ
死亡後の郵便物対応は、放置するとトラブルや防犯リスクにつながる重要な問題です。
転送制度が使えない以上、現地で確認し、差出人ごとに対応していくことが基本となります。
故人の情報を守り、余計な負担を避けるためにも、早めの対応を心がけましょう。
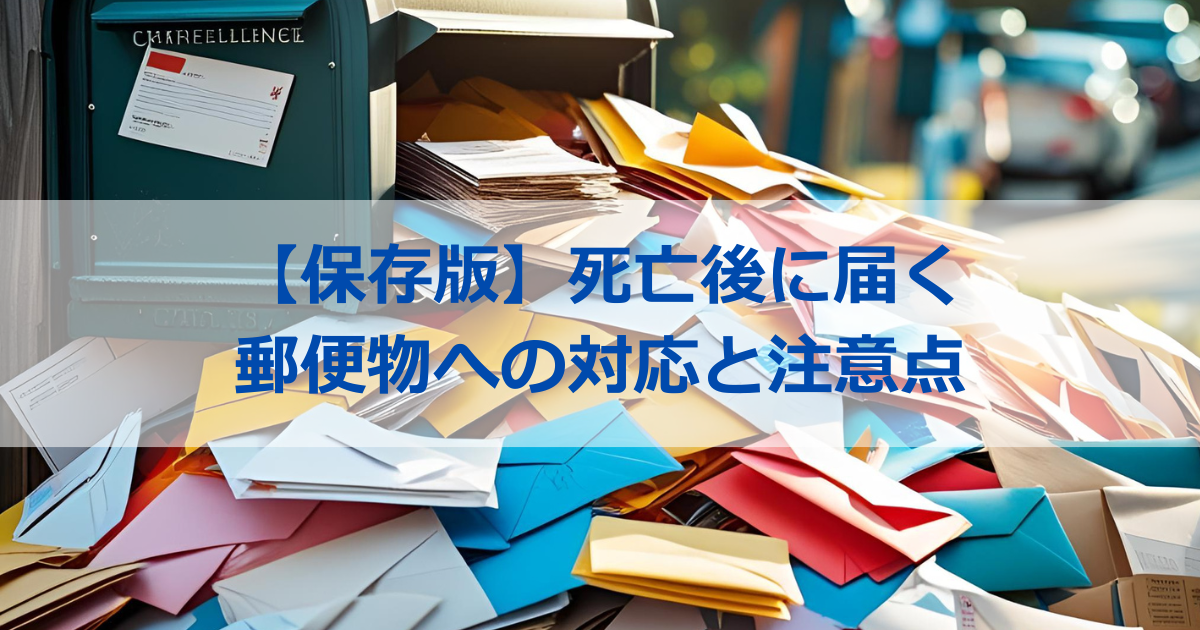
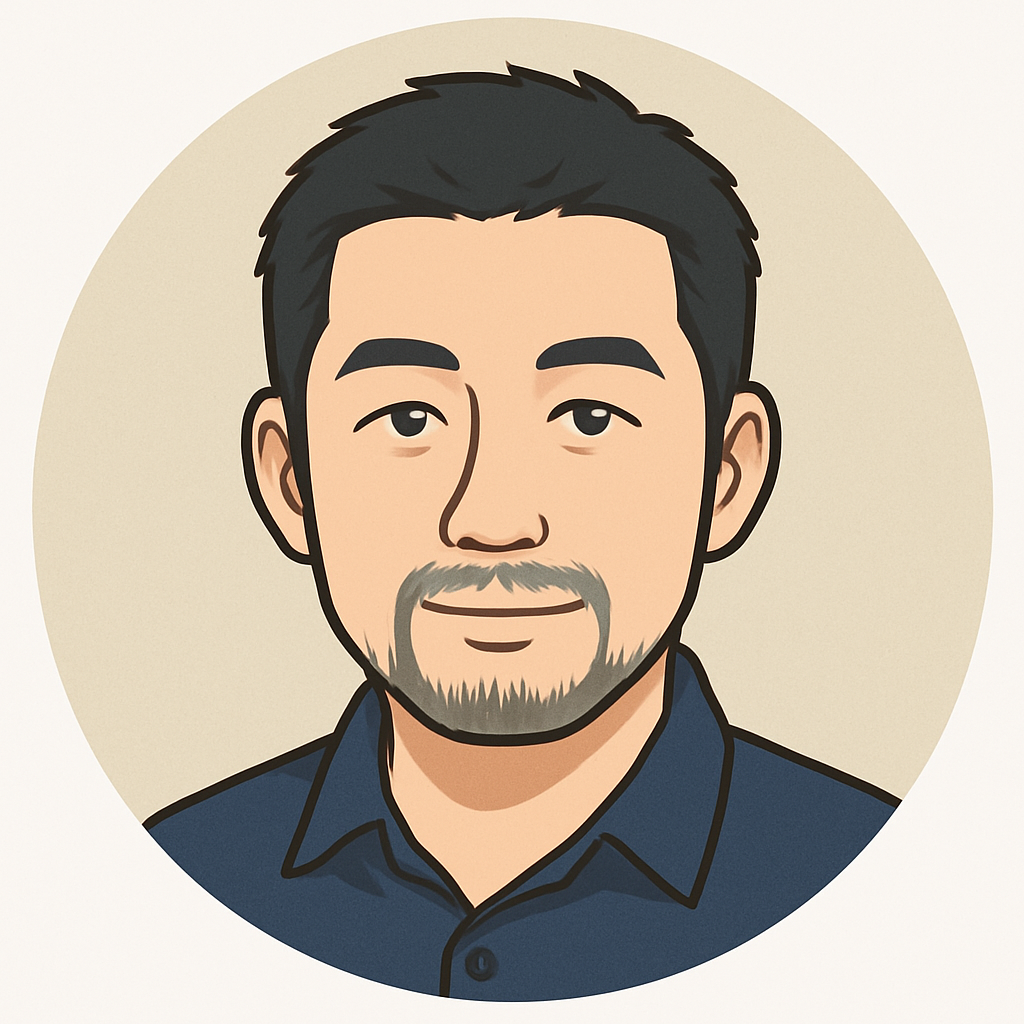
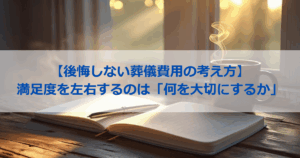


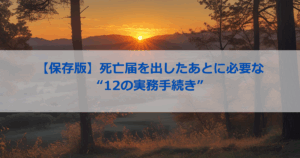

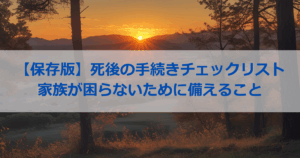
コメント