目次
はじめに
ご家族が亡くなったあとは、相続や不動産登記、遺言の検認など、法的な手続きがいくつも発生します。
この記事では、それらの法的手続きとは別に、日常生活の中で必要となる実務的な観点から整理しています。
健康保険の喪失や年金の停止、各種契約の解約など、「あとでやろう」と後回しにしていると、思わぬ不利益につながることがあります。
どの手続きから着手すればよいか──。その流れを抜けもれなく把握するための道しるべとして、この記事を参考にしてください。
死亡届提出後に必要な12の実務手続き
1. 健康保険の喪失手続き
- 市区町村や勤務先の健康保険組合など、加入していた制度に応じて届け出を行います。
2. 介護保険の喪失・停止
- 要介護認定を受けていた場合、介護保険証を返納し、利用サービスを停止します。
3. 年金受給の停止
- 日本年金機構または市区町村の窓口で、受給停止の手続きが必要です。
4. 未支給年金の請求
- 亡くなった月までの年金は「未支給年金」として、遺族が請求できます。
5. 遺族年金などの請求
- 一定の条件を満たせば、配偶者や子どもが遺族年金を受給できます。
6. 世帯主の変更
- 世帯主が亡くなった場合、住民票のある市区町村で世帯主変更の手続きが必要です。
7. 医療費・高額療養費などの申請
- 高額療養費や埋葬料の請求が可能な場合があります。保険者ごとに異なるため、確認が必要です。
8. 生命保険金の請求
- 加入していた各保険会社に対して、死亡保険金の請求を行います。
9. 公共料金・サービスの名義変更や解約
- 電気・水道・ガス・電話・携帯・クレジットカードなどの名義変更や解約を行います。
10. 所得税関連の手続き
- 確定申告が必要な場合は、「準確定申告」の手続きを行います。
11. 相続税関連の手続き
- 相続財産の有無や額によって、相続税申告が必要です(通常は10か月以内)。
12. サブスクリプションやアプリ等の解約
- 放置すると課金が継続されたり、個人情報が残ったままになるリスクがあります。
おわりに
死亡後の手続きは多岐にわたり、長期間にわたることもあるため、情報を整理し、全体の流れを把握しておくことが大切です。
本記事が、少しでも不安や負担を軽くする助けになれば幸いです。
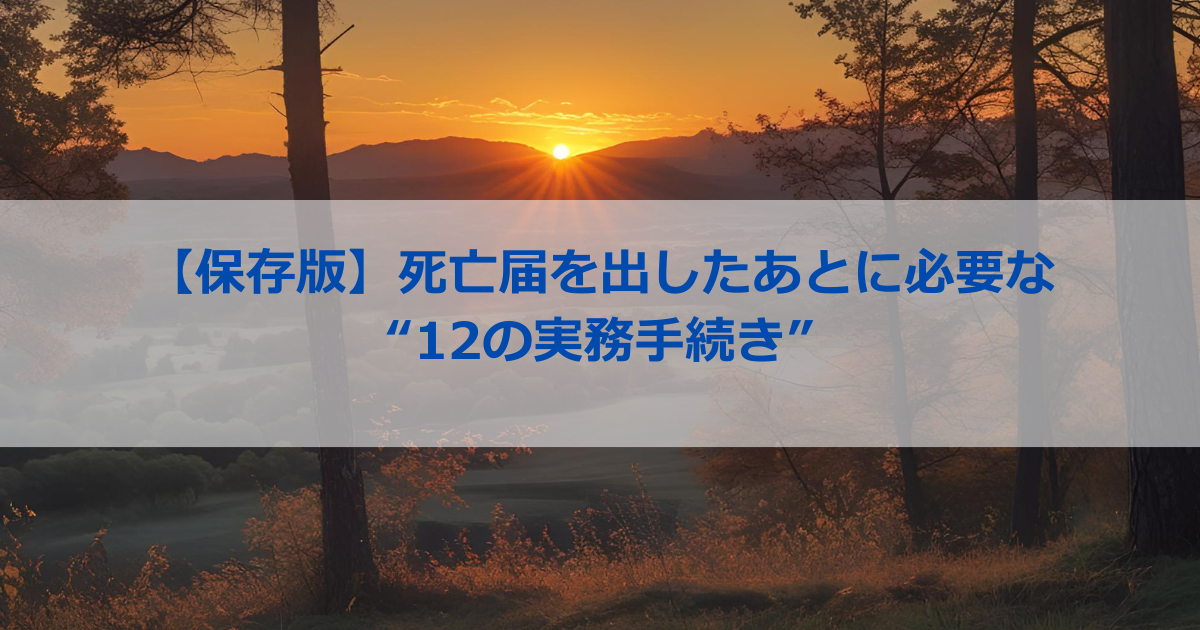
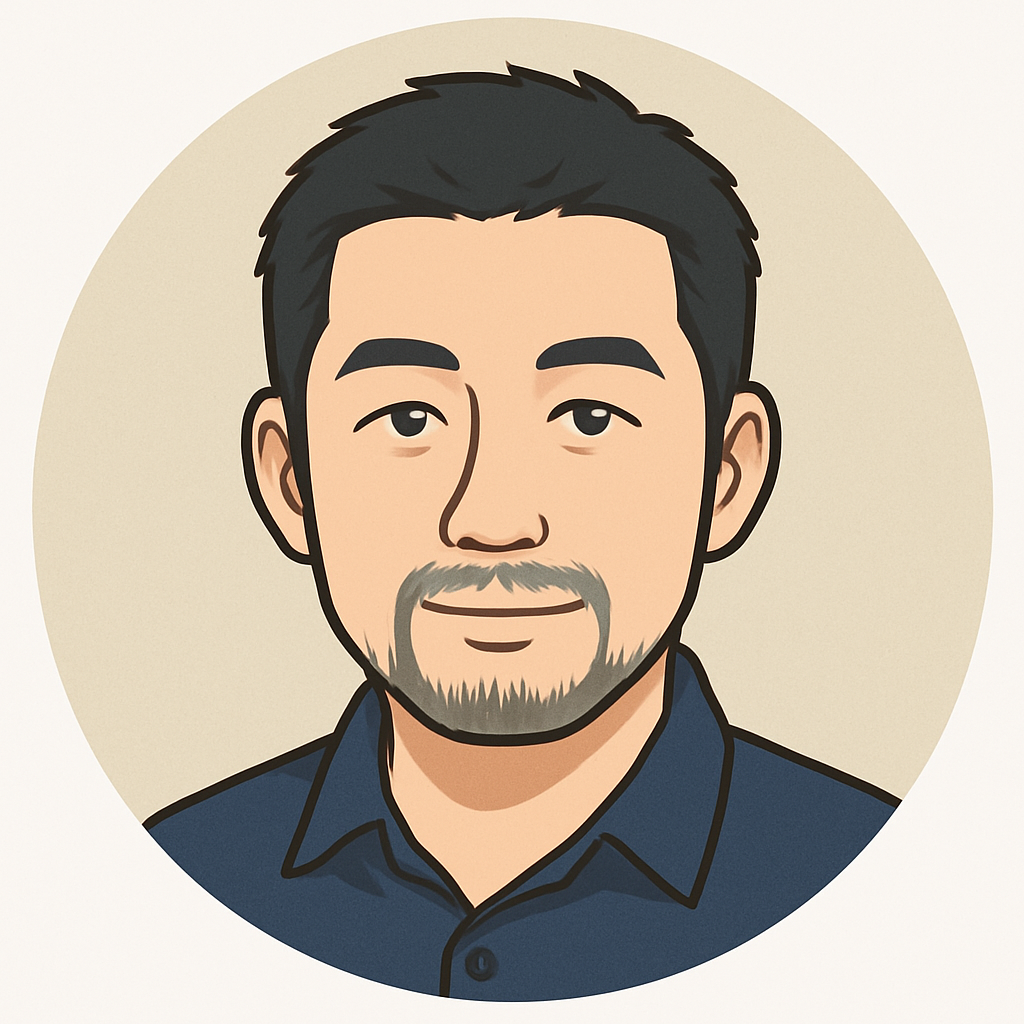
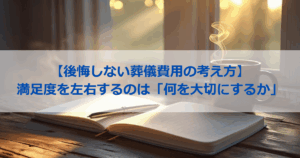

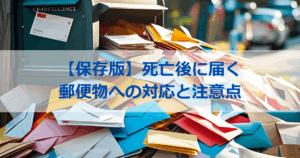


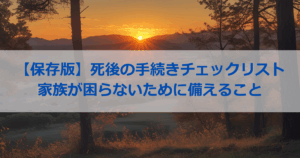
コメント