亡くなった人の銀行口座、どうすればいい?
身近な家族が亡くなったとき、意外と多くの方が戸惑うのが「銀行口座の手続き」です。
葬儀や届け出が落ち着いた頃、生活費の引き落としや預金の引き出しができなくなり、慌てて手続きを始める…というケースも少なくありません。
この記事では、亡くなった方の銀行口座がどうなるのか、そして解約・名義変更の正しい流れと注意点を、わかりやすく整理します。
1.銀行口座はいつ凍結される?
亡くなった人の銀行口座は、金融機関が死亡を把握した時点で凍結されます。
役所から銀行に連絡がいくわけではなく、家族や関係者が死亡を知らせたり、新聞記事や戸籍照会などで銀行が死亡を知った時点で凍結される仕組みです。
2.口座が凍結されるとどうなる?
口座が凍結されると、次のような取引がすべて停止します:
- ATMからの出金
- 自動引き落とし(光熱費・家賃・サブスク等)
- ネットバンキングの操作
- 振込の入出金
生活費や公共料金の引き落としが止まると、実生活に影響が出ることもあるため、注意が必要です。
3.死亡後の「引き出し」はできるのか?
原則として、死亡後に家族が勝手に引き出すことはできません。
仮に通帳やカードを使って引き出した場合、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。
ただし、一部の金融機関では「仮払い制度」を利用できることがあります。
これは、相続人であることを証明できれば、一定額まで預金を引き出せる制度です。
利用には条件があるため、事前に該当銀行の対応を確認しましょう。
4.解約や名義変更の流れ
銀行口座の相続手続きは、以下のように進みます:
- 銀行に死亡を連絡し、口座が凍結される
- 相続人を戸籍などで確定する
- 遺産分割協議書、または遺言書を用意する
- 必要書類をそろえ、銀行の相続手続き窓口に提出する
- 審査のうえ、口座の解約または名義変更が完了する
必要な書類は、銀行によって多少異なりますが、以下のようなものが基本です:
- 死亡診断書や除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(または遺言書と検認書)
- 相続人の印鑑登録証明書
- 本人確認書類
- 銀行所定の相続手続依頼書類
5.よくある誤解と注意点
- 「家族が勝手に引き出していい」は誤解です
預金は相続財産であり、法定相続人全員の共有資産と見なされます。 - 共同名義口座は別の扱いになります
金融機関によって対応が異なるため、事前に確認が必要です。 - 放置された口座は休眠預金として扱われる可能性があります
相続できなくなるわけではありませんが、受け取り手続きがやや煩雑になります。
6.生前にできる備え
遺族が手続きに困らないためには、次のような備えが役立ちます:
- 利用していない口座は解約しておく
- どの銀行に口座があるかをリストにしておく
- エンディングノートに銀行名・支店名・口座種別を書き残す
また、通帳や印鑑、キャッシュカードの保管場所も、家族がわかるようにしておくと安心です。
最新の情報について
制度や対応は変更されることがあります。必要に応じて、以下の機関で最新情報をご確認ください:
- 死亡届・戸籍関連:法務省
- 健康保険・年金・介護保険:厚生労働省、日本年金機構
- 税金・相続税・準確定申告:国税庁
- 口座の相続手続き・必要書類:各銀行窓口(全国銀行協会なども参考)

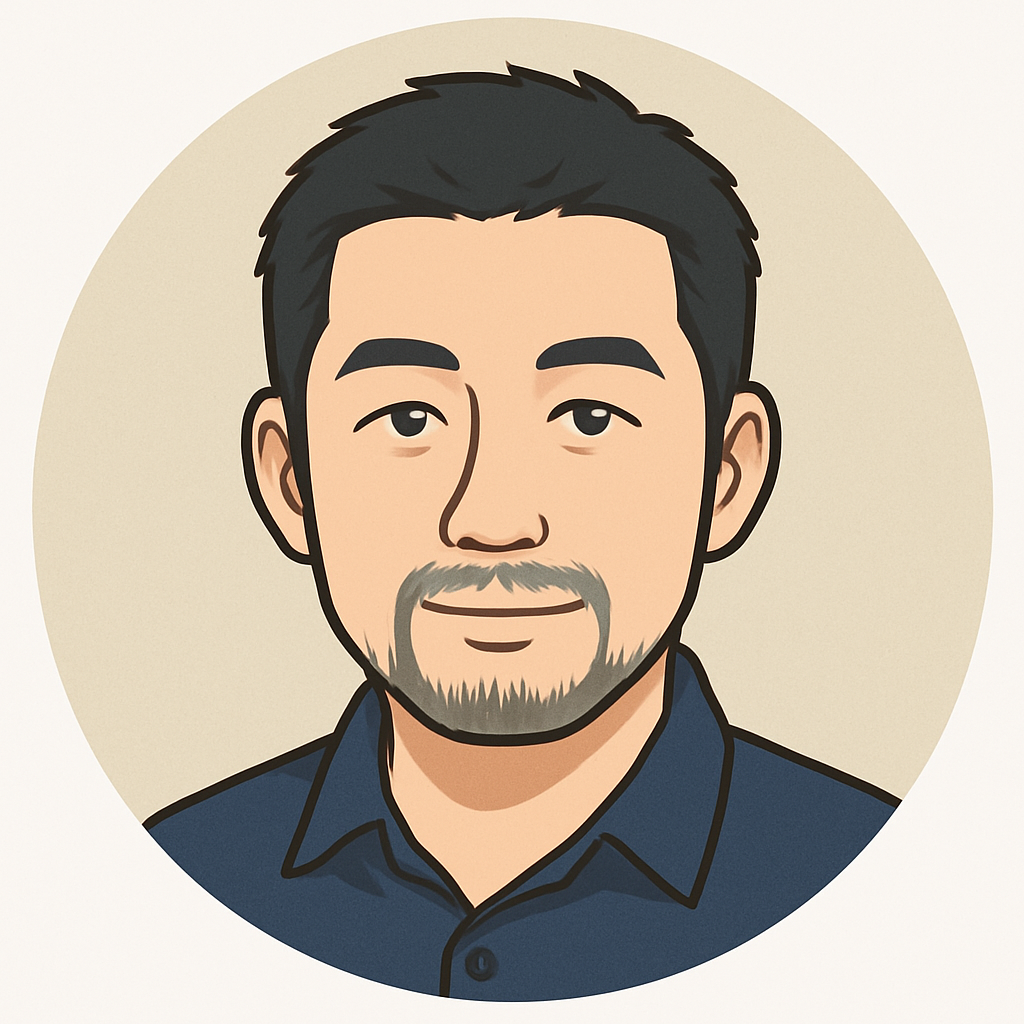
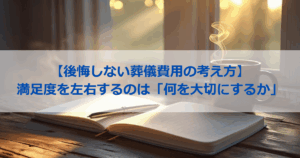

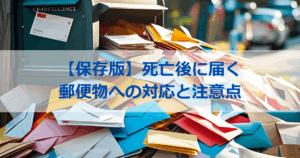

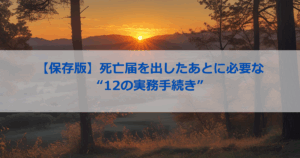
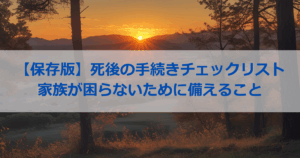
コメント