目次
はじめに
家族が亡くなったとき、遺された人には多くの手続きが必要になります。
葬儀の準備や市区町村への届出、年金や保険、税金の申告など、やるべきことは時期によって異なり、短期間で対応しなければならないものもあります。
この記事では、そうした死後の手続きを、「いつ・何を・どこで」行えばよいのかをわかりやすくまとめました。
必要な時に迷わないように、ぜひ一度目を通しておくことをおすすめします。
死後の主な手続きの流れと時期
■ 死亡後すぐ(~7日以内)
- 死亡診断書または死体検案書の受け取り
病院または医師から発行されます。死亡届の提出に必要です。 - 死亡届の提出
死亡後7日以内に、市区町村の役所に提出します。
火葬許可証の発行手続きも同時に行います。 - 葬儀・火葬の準備
葬儀社との打ち合わせや会場手配などを進めます。
■ 死亡後2週間以内
- 健康保険・介護保険の資格喪失届出
市区町村や勤務先を通じて、保険証の返却などを行います。 - 年金の手続き
公的年金の受給停止、未支給年金や遺族年金の請求準備を進めます。
必要書類は多いため、年金事務所などで事前確認がおすすめです。 - 世帯主の変更(必要な場合)
住民票の世帯主が変わる場合は役所で手続きします。
■ 死亡後1か月以内
- 銀行口座・クレジットカードの対応
死亡が確認されると、本人名義の口座は凍結されます。
凍結後は相続人でなければ手続きできません。 - 公共料金・サブスクなどの名義変更または解約
電気・ガス・水道や携帯電話、インターネット、定期購入サービスなど。
契約者が亡くなった場合、解約証明や死亡診断書のコピーが必要になることがあります。 - 生命保険金の請求
保険証券や契約番号を元に、速やかに保険会社に連絡します。
■ 死亡後4か月以内
- 準確定申告(故人の所得税申告)
亡くなった方に収入があった場合、死亡後4か月以内に所得税の申告・納税を行います。
相続人が手続きを引き継ぐことになります。
■ 死亡後10か月以内
- 相続税の申告・納付
課税対象となる遺産がある場合、死亡から10か月以内に申告と納税が必要です。
遺産分割協議もこの期間内にまとめるのが望ましいです。
■ 死亡後2年以内
- 遺族年金・未支給年金の請求
死亡した方の年金の未支給分や、遺族が受け取れる年金は2年以内が期限です。
この期限を過ぎると受け取れなくなる可能性があるため、早めの確認をおすすめします。
補足:デジタル遺品の整理
スマートフォンやパソコンに関する手続きも、近年は重要です。
- 写真や重要なファイルの保存先やパス(フォルダの場所)を、わかりやすく整理しておく
- 定期的に不要なファイルやメールを削除し、外付けHDDなどにバックアップを取ると家族の負担が軽減されます
- SNSやネットバンキング、アプリなどのアカウント情報は、別に安全な形で管理しておくことが理想です(IDやパスワードはエンディングノートに残すなど)
最新の情報について
この記事では、できるだけ正確な情報をもとに手続きをまとめていますが、制度や手続き内容は変更されることがあります。
具体的な方法や必要書類は、実際に申請する際に各公的機関の最新情報をご確認ください。
▼ 主な確認先(分野別)
- 死亡届や戸籍に関すること:法務省
- 死亡診断書・健康保険・介護保険:厚生労働省
- 年金・遺族年金・未支給年金の手続き:日本年金機構
- 所得税の準確定申告・相続税の申告:国税庁
- 不動産の名義変更(相続登記):法務省
- 生命保険金の請求手続き:各生命保険会社(手続きの流れは生命保険協会サイトも参考になります)
- 公共料金・契約サービスの対応:各事業者・市区町村窓口
まとめ
死後の手続きは、時間的制約があるうえに、精神的にも負担の大きなものです。
だからこそ、生きているうちに情報を整理しておくことが、残される人への大きな助けになります。
手続きに必要な書類や連絡先を一覧にしておいたり、エンディングノートを活用したり、できることから始めてみてください。
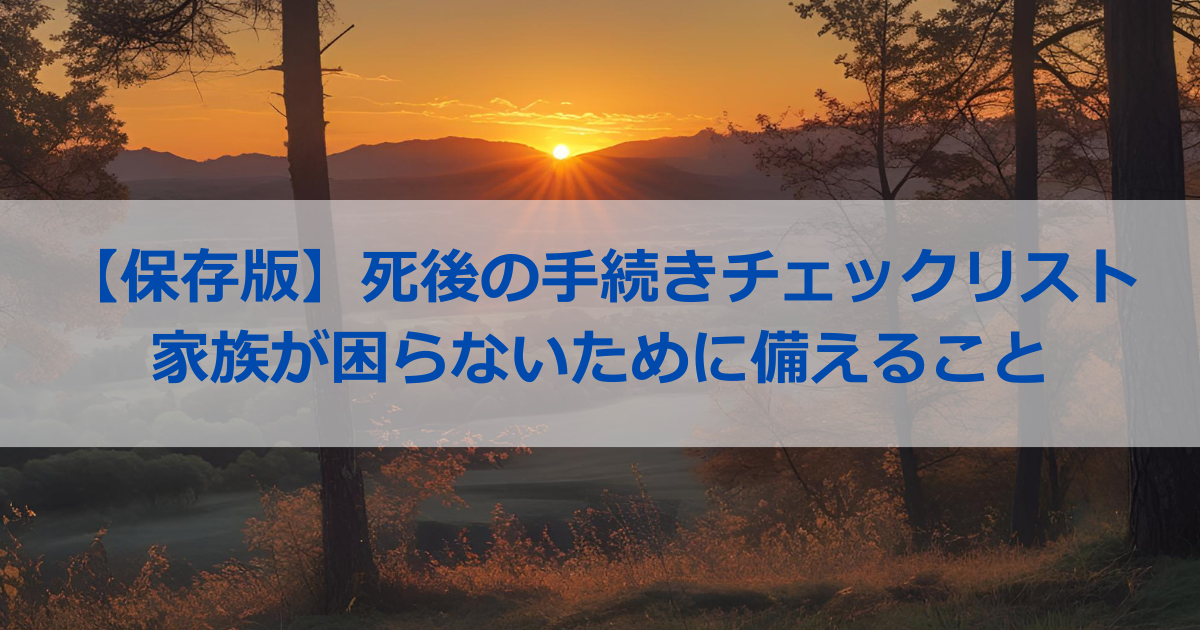
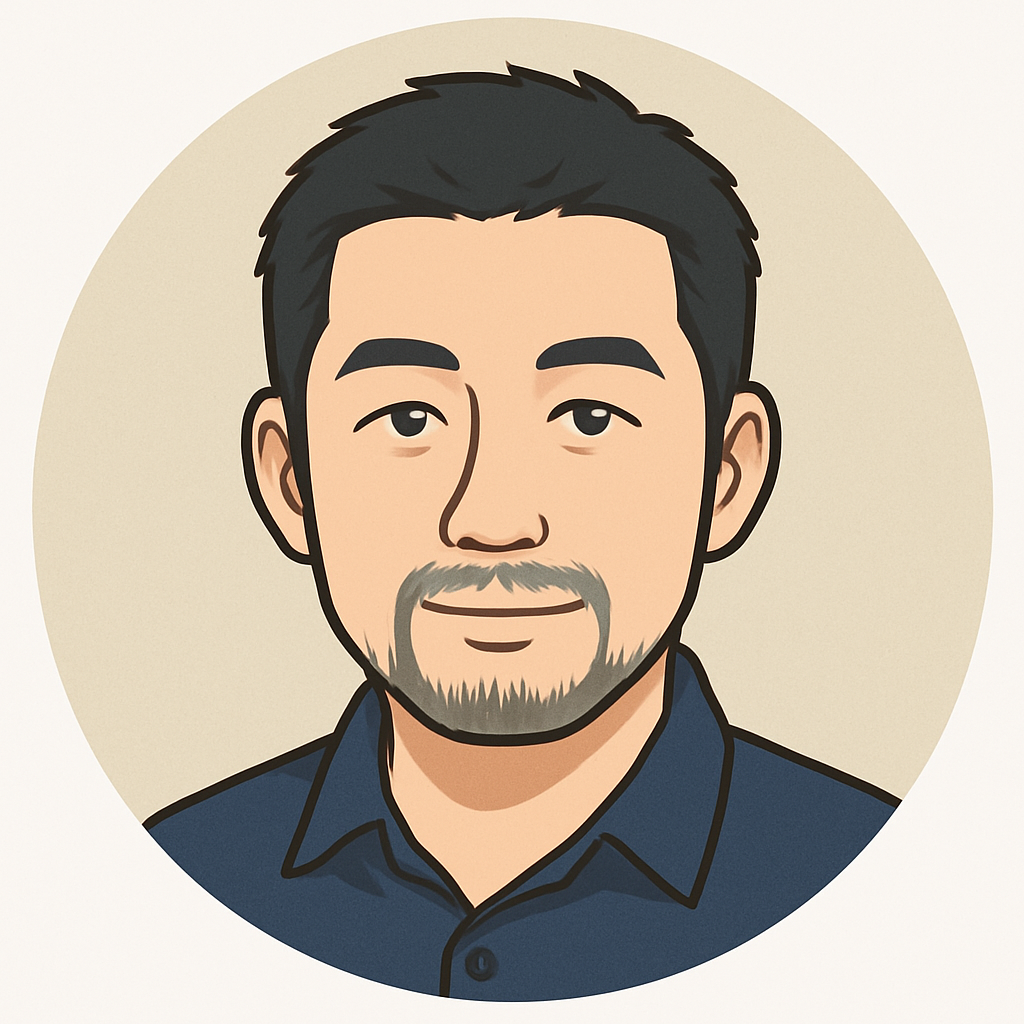
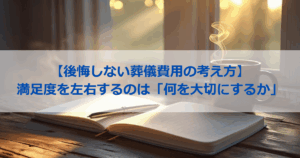

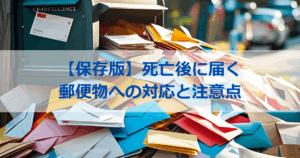

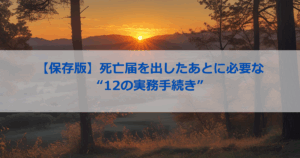

コメント